「この商品、いくらで売ればいいかアドバイスいただけませんか?」と頻繁に耳にします。
商品やサービスをつくっても、「値段をいくらにするか」は悩ましい問題です。
安くしすぎると利益が出ない。高くすると売れない。
この“ちょうどいい価格”を見つけるのが、商売の難しさでもあり、面白さでもあります。
とはいえ、感覚や思いつきで値決めをしていると、売れても利益が残らなかったり、お客様に選ばれなかったりしてしまいます。
この記事では、スモールビジネスの経営者が「価格をどう決めるべきか」を考えるために、3つのポイントに分けてご紹介します。
「なぜこの価格なのか」に自信が持てるようになれば、商売の軸がぶれにくくなります。
価格設定は“ビジネスモデル”とセットで考える
値段の正解は、「何を売るか」だけでは決まりません。
どう売るのか、どんな形で利益を出すのか──つまり「ビジネスモデル」によって、適した価格の考え方はまったく変わります。
たとえば、数をさばくビジネスもあれば、少数の顧客に高単価でしっかり価値を届けるスタイルもあります。
まずは、自分のビジネスがどのタイプに近いかを見極めましょう。

何でもかんでも安くすればいいって訳ではないんですね?
はい!赤字スレスレですと事業の継続が難しくなります!
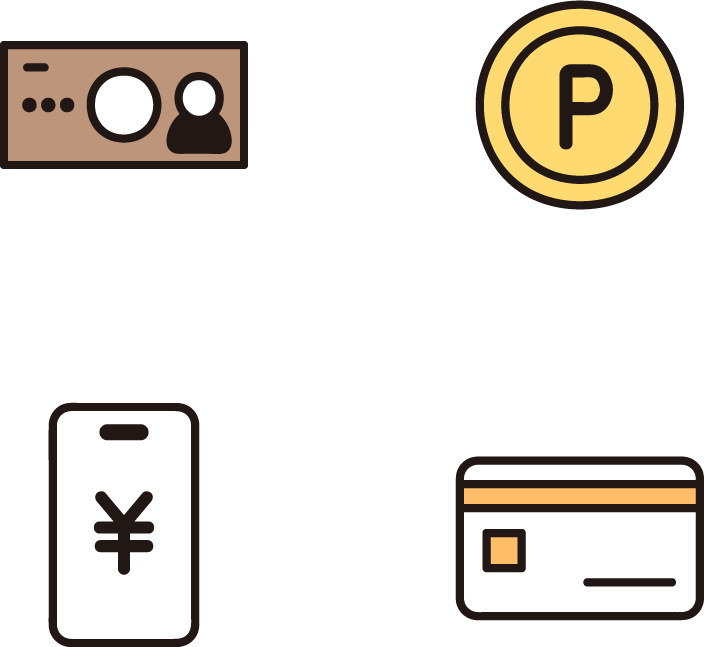
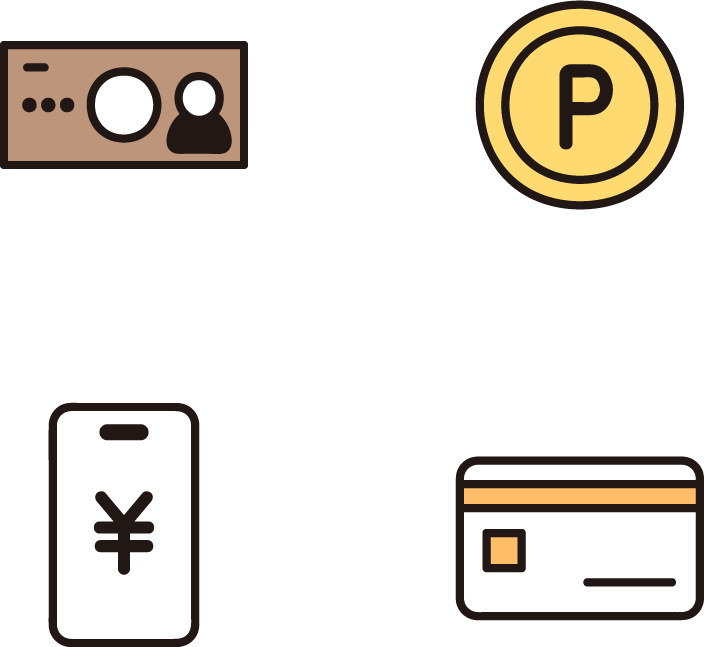
① 数量・回転率重視型(安く・たくさん売る)
このタイプは、単価を抑えて数をこなすことで利益を出すスタイルです。
飲食店のランチ営業や雑貨販売、サブスク(定額制サービス)などがこれにあたります。
ポイントは「価格のわかりやすさ」と「買いやすさ」。
回転率を上げるには、迷わず買える価格帯にすることと、集客の仕組みをしっかり整える必要があります。
② 高単価・価値提供型(少なく・しっかり売る)
お客様に対して、商品やサービスをじっくり丁寧に届けて、そのぶん高単価でも納得してもらうモデルです。
美容室、治療院、士業、コンサルティングなどが代表的です。
「価格の理由」が納得できるように、価値を伝える工夫が不可欠です。
口コミや事例、接客の丁寧さなど、“信頼”が価格を支えます。
③ ハイブリッド型(商品ごとに分けて考える)
サービスと物販を組み合わせている場合や、商品の幅が広いビジネスでは、
「この商品は回転重視」「これは価値で売る」と使い分けることも大切です。
例えばランチは認知拡大を目的として回転重視、ディナーはゆっくり落ち着いた時間を過ごしていただく為に価値提供などです。
すべて同じ考えで価格を決めようとすると無理が出るので、
“売り方”と“届け方”に合わせて、価格設定も柔軟に考えてみましょう。
値決めに使える「価格設定の3つの視点」
自分のビジネススタイルが見えてきたら、次は「いくらにするか」を考える番です。
そこで役立つのが、「価格設定の3つの視点」。
この3つをバランスよく考えることで、納得感のある価格が見えてきます。



まずは赤字にならない金額を理解する必要があるってことですね?
その通りですね!その次は競合や価格が説明できるかというのが重要です。


① コストの視点(赤字にならない価格か)
まず大前提として、利益が残らなければ商売は続きません。
原材料費や外注費、家賃、水道光熱費、広告費…見落としがちな細かいコストもすべて含めて考えます。
特に注意したいのが、「自分の時間や手間」もコストだということ。
値決めのときは、「その価格でちゃんと利益が残るか?」を冷静にチェックすることが重要です。サービス業などで安易に安価にすると赤字はおろか、体調を壊しかねないので注意してくださいね!
② お客様の視点(納得してもらえるか)
お客様にとって大切なのは、「安いか高いか」ではなく、「その価格に納得できるかどうか」です。
同じ5,000円でも、「ただのシャツ」よりも、
「抗菌加工で清潔が長持ちし、たとえば入院中など洗濯が頻繁にできない状況でも安心して着られるシャツ」
と伝えれば、印象は大きく変わります。
「この価格なら納得」と思ってもらえるように、価格だけでなく“伝え方”までセットで考えましょう。
③ 市場の視点(他と比べてズレていないか)
最後は、周りの相場とのバランスです。
競合と比べて明らかに高すぎたり、逆に安すぎて「なぜこんなに安いの?」と不安を与えたりしていないか確認します。
もちろん、同じ価格にする必要はありません。
ただし、高くするなら高い理由、安くするなら安い理由が「伝わる状態」になっていることが大切です。
値決めに迷ったときに立ち返る「3つの問い」
ここまできたら、価格の方向性はある程度見えているはず。
でも、いざ実際に価格を決めるとなると、不安や迷いが出てくるのも事実です。
そんなときにおすすめなのが、「自分に問いかける」こと。
最終確認として、次の3つを使ってみてください。



基本的にはさっきの「価格設定の3つの視点」ですね!
正解です!しっかり自問自答が大切です。
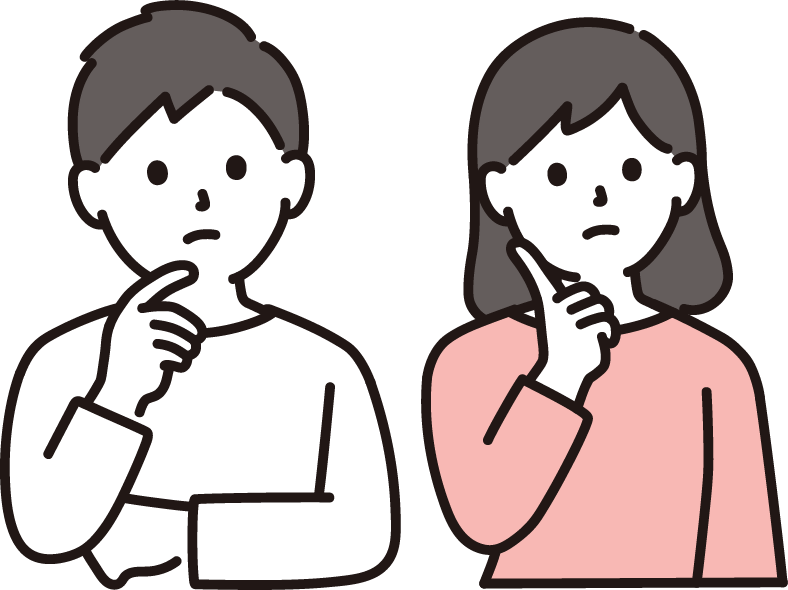
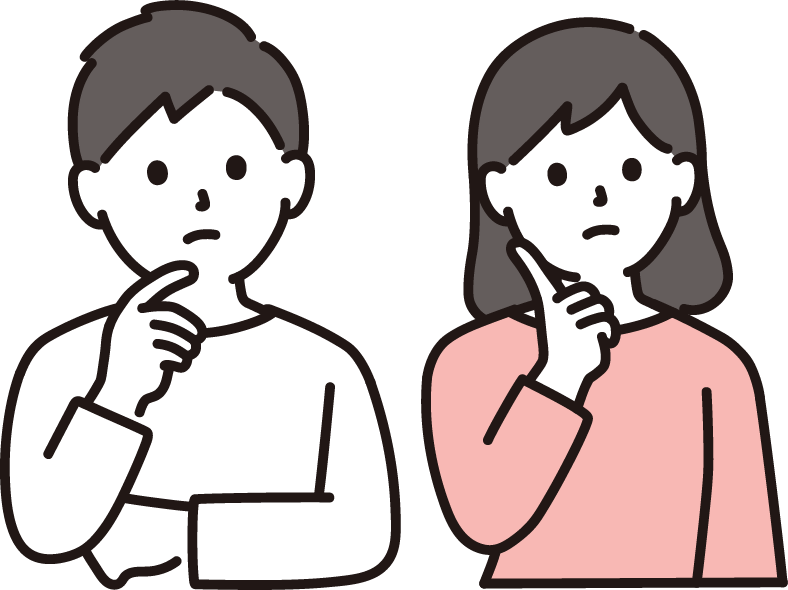
① この価格で、ちゃんと利益が残りますか?
目の前の売上ではなく、売れた後にちゃんと利益が残るかを見直しましょう。
手間がかかる商品なのに安すぎたり、想定より工数がかかって利益が出ない、ということがないかを確認してください。
② お客様は、この価格に納得してくれそうですか?
価格に対して「高いか、安いか」と感じるのは、あくまで“印象”です。
そしてその印象は、「価格そのもの」ではなく、「その価格でどんな価値が得られるか」によって決まります。
たとえば、同じ5,000円でも──
・ただのTシャツ:ちょっと高いかも?
・肌ざわりがよく、デザインが非常に優れたシャツ:お得に感じる
・乾燥機にかけても傷みにくい:それなら納得!
お客様は、金額だけを見て判断しているわけではありません。
“価格に見合ったメリット”がしっかり伝わっていれば、「高いけど、これなら仕方ないよね」と感じてもらえるんです。
このパートでは、「価格に対して、ちゃんと理由を伝えられているか?」を見直してみましょう。
見せ方、言葉、説明、事例──伝え方ひとつで、価格の印象はガラッと変わります。
③ 他と比べて違和感はありませんか?
自分の商品やサービスの価格を決めるとき、意外と見落としがちなのが「まわりとのバランス感」です。
競合や似たジャンルの商品が3,000円前後なのに、自分の商品だけが10,000円だったらどうでしょう?
何の説明もなければ、「なぜ?」と疑問を持たれ、選ばれなくなってしまう可能性があります。
逆に、相場より極端に安すぎる場合も「品質、大丈夫かな…」と不安を与えてしまうこともあります。
ただし、ここで誤解してほしくないのは、「他と同じ価格にすべき」という話ではありません。
むしろ大切なのは、「この価格になっている理由を、自分の言葉でちゃんと説明できるかどうか」「お客様に“納得してもらえる状態”になっているかどうか」なんです。
価格だけがひとり歩きして、価値の説明が置き去りになっていないか。
今一度、価格と価値の“つり合い”を冷静に見直してみましょう。
📩 メルマガで、売上アップのヒントをお届けします!
価格設定や商品づくり、販促のアイデアなど、スモールビジネスの現場で役立つ情報を、メルマガでお届けしています。
- 売上を伸ばしたいけど、何から始めればいいか分からない
- 商品やサービスの魅力を、うまく伝えられていない気がする
- 価格を上げたいけど、お客様にどう説明すればいいか悩んでいる
そんなお悩みをお持ちの方に、具体的なヒントや事例をお届けしています。
登録は無料ですので、ぜひお気軽にご登録ください。
メルマガ登録お待ちしております!
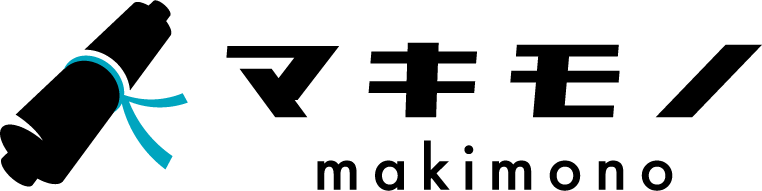
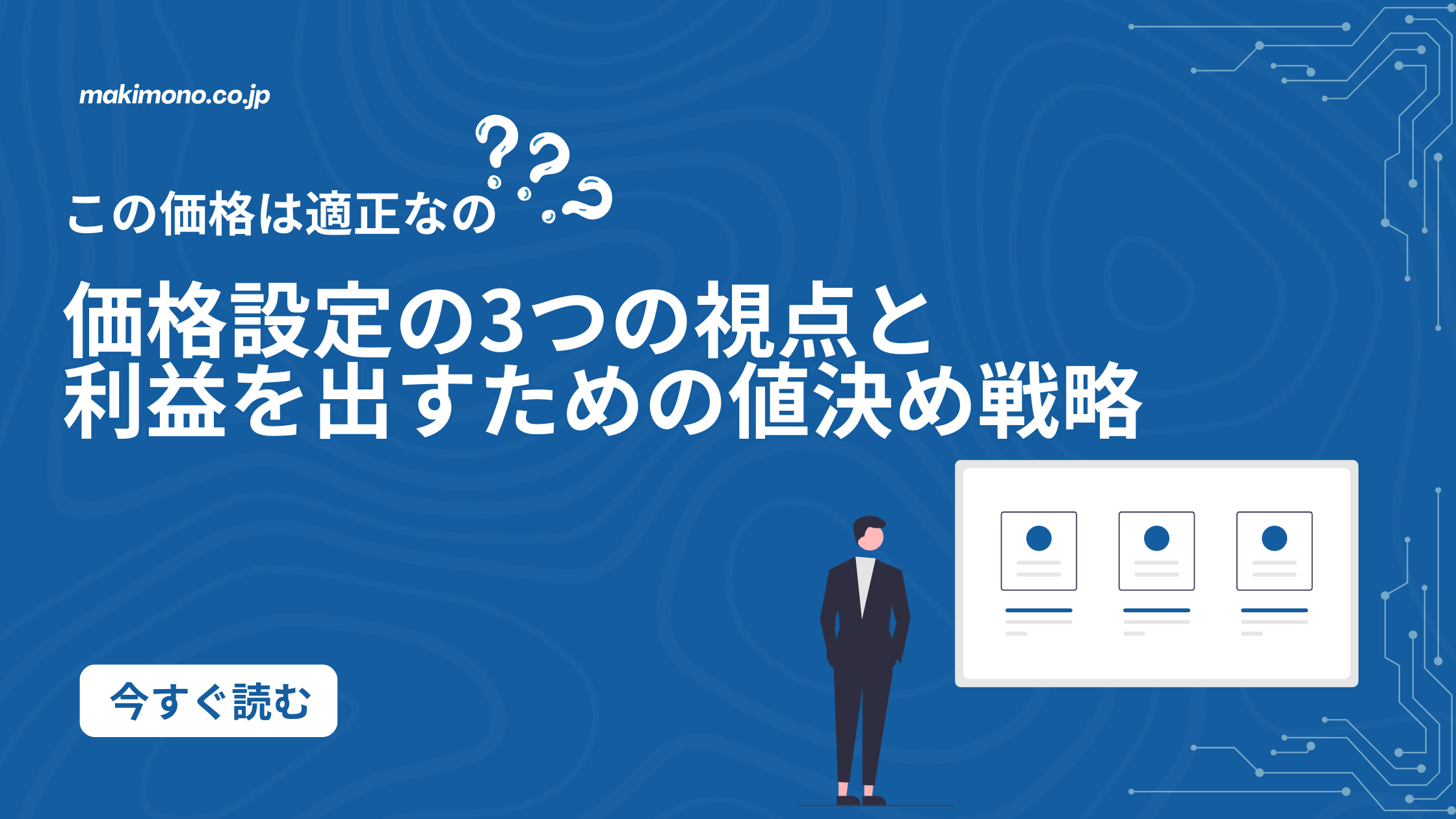

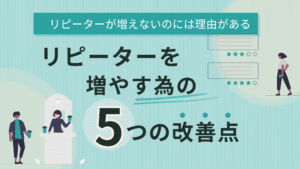

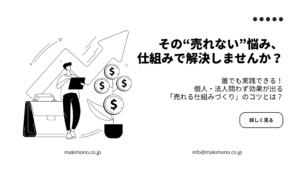


コメント